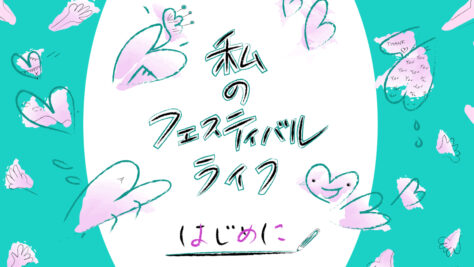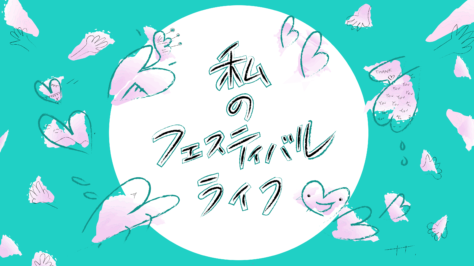元日で能登半島地震から1年が経ちました。さまざまな報道やSNSで「復興が全然進んでいない」という声を聞いたことがあるのではないでしょうか。アースガーデン冬2025では、震災直後から継続的に支援活動に取り組んでいるみなさんをお呼びし、トークセッションやブース出店をしていただきました。
今回は当日のトークセッションのレポートをお届けします。2つ目は輪島市町野町で「町野復興プロジェクト」を立ち上げた、山下祐介さんと、石川県七尾市で「おらっちゃ七尾」の代表として活動する今井健太郎さんに実際の活動の様子を聞きました。自分がボランティアに行ったらどんなことができそうか、想像しながら読んでみてください。
自分たちが住む町だから
── 自己紹介をお願いします。
山下 こんにちは。山下と申します。私は被災地である輪島市町野町の町民で、私が代表を務める「町野復興プロジェクト」は、町民が自ら立ち上げた団体です。「自分たちが住む町だから、自分たちで良い町に復興させよう」という思いから、2024年の2月に立ち上げました。地震で倒壊した家が多く、町中は瓦礫だらけまだ町中が泥だらけで、地域全体が停電していたころです。現在は、民間のボランティアセンターも設置し、3カ月で3,400名ものボランティアさんに来てもらいました。今もさまざまな活動を続けています。

今井 民間ボランティアセンター「おらっちゃ七尾」の運営や、「一般社団法人 sien sien west」の代表を務めております、今井です。この10年ほど、自然災害が起きた各地に駆けつけ、泥かき、家具の運び出し、壁や床剥がしなど災害支援をしてきました。能登の支援は2024年の1月3日からスタートし、現在も継続的に支援を続けています。

自分たちよりも被害の多い場所に行ってあげて…
── ボランティアセンターを立ち上げた経緯を教えてください。
山下 1月1日の地震被害は、多くの人が報道などでご存知かと思いますが、その後9月に発生した能登半島豪雨が、地震と同じくらい深刻な被害をもたらしたことを知っている人は少ないかもしれません。亡くなった方は地震のほうが多かったものの、多くの人が仮設住宅に避難していたため助かっただけで、元々住んでいた場所にいたらさらに犠牲者が増えていた可能性があります。それほど甚大な被害でした。中心地にある町役場や小学校、中学校など、街中が泥だらけになり、床上浸水しました。
1年の間に2度の大きな自然災害に見舞われ、「本当に心が折れた」という言葉が「おはよう」の挨拶のように交わされる状況でした。だからこそ、雪が積もる前に、地震の前の状態とはいかないまでも、少なくとも豪雨前の状態に町野を戻したいという思いで、ボランティアセンターを立ち上げました。経験は全くありませんでしたが、多くの方の協力を得て、なんとか運営してきました。

今井 私たちが活動する七尾市は、表立った被害が少ない地域でした。1月3日に能登入りした時点では、七尾より奥の被害が深刻で、七尾で支援物資を下ろし、それを他のボランティアチームに託すという形で支援を始めました。その後1月7日に奥まで進んでみると、深刻な被害の実態を目の当たりにしました。
一方、七尾市も被害がないわけではなく、避難所には何百人もの人が避難し、倒壊した家屋は1万5,000件を超えます。ただ、表通りの被害が少なかったため、外見だけでは被災の実態が見えにくい地域でした。七尾の人たちも「自分たちより被害の大きい場所に行ってあげて」と遠慮しがちで、時には諦めのような雰囲気すら感じました。そこで、七尾の支援が自分の役目だと考え、公的なボランティアセンターが閉じた後、その役割を引き継ぐ形で活動を続けています。
「できない・諦める」から「やれるかも」へ
── どんな人が参加されてますか?
山下 本当にさまざまな方がいらっしゃいます。普段は会社で事務をしている方、経営者、年齢も小学生から70代まで幅広いです。特に、過去に被災された方が「前にボランティアに助けられたから、今度は自分が助ける側になりたい」と関西や東北、熊本などから駆けつけてくださいました。
今井 私たちのところも同様で、一度ボランティアを経験した方が何度も来てくださるケースが多いです。まずは一度参加してみてほしいですね。一度経験すると、次回からのハードルが下がると思います。
── これからどんな活動をしていくのかを教えてください。
山下 雪の時期が過ぎたら、詰まってしまった用水路の泥掻きを再開しなければと思っています。スコップを使った力仕事もありますが、仮設住宅でのコミュニティビルディングも必要になってくるはずです。まだまだ仮設住宅に住んでいる方が多く、震災から1年を超えて少し気持ちが沈んでいる方も少なくありません。地元の方と話す、コミュニケーションを取るということにもサポートいただけれたらうれしいです。ただ、僕らの団体は、地域住民が集まりなので、活動とは別に仕事もあって、1から10まで段取りするほど余裕もないのが現実でして…。「場所さえあれば、あとはこっちでやりますよ」というケースだと本当に助かります。そういう事情で、春以降のボランティアの受け入れは、まだ具体的には決まっていないのです。準備ができたらすぐにお声がけしますのでぜひSNSなどをチェックいただければと思います。
今井 1年前も今もまったく変わらず、家の中からの家財道具の搬出が主な活動です。震災直後はとにかく使えないものを搬出していましたが、今は新しい家の再建のために古い家の解体の前作業としての運び出しが多くなっています。ただ今後は、町の復興というところにもフォーカスしていく必要があるだろうと思っています。作業だけでは復興できない。コミュニティのこと、仕事のこと、そういった生活に必要なことの支援が始まっていくと思います。ここからはさまざまな業種のプロフェッショナルと連携していくことにもなるでしょう。例えばタンスを運ぶにしたって、一人じゃ動かせなくても、もう一人加われば運び出せる。一人でも多くの人に来てもらって、関わってもらって「できない・諦める」から「やれるかも」と思える瞬間を増やしていきたい。そういった何かしらの希望の届けられるような支援活動を、今後も続けていきたいなと思っています。
町野復興プロジェクト
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた、輪島市の東部に位置する町野町地区で、地元住民が発災1カ月後に設立した団体です。『町野をワクワク・楽しい町にする!』をモットーに、復興及び持続可能なまちづくりに関する活動を行なっています。イベント等を通じた実証実験を行なうなど、今後の地域に必要なモノ・コトは何かを考え、魅力ある地域となるように日々活動しています。
https://www.instagram.com/machino.2411/
民間災害ボランティアセンターおらっちゃ七尾
民間災害ボランティアセンターおらっちゃ七尾は、災害支援を専門とする団体が民間の力で立ち上げた災害ボランティアセンターです。七尾市や社会福祉協議会、11の団体と連携し活動を行っています。家屋の片付けなどの作業系支援に加え、地域コミュニティ再建のためのマッサージやお茶会などのソフト系支援も展開。高齢者や困窮世帯など災害弱者と呼ばれる要配慮者世帯などにも注力し、誰一人取り残さない復興を目指しています。運営は一般社団法人sien sien westが担っています。